大切な家族が亡くなったとき、悲しみの中でも避けられないのが各種の手続きです。
特に銀行口座や保険、税金、年金などお金に関わる手続きは期限が決まっているものが多く、遅れると損をしたりトラブルになる可能性があります。
この記事では「家族が亡くなったときにやるべきお金のこと」を、優先順位・期限・必要書類とともに解説します。

すぐにやるべき手続き(期限なしでも早めが安心)
1. 銀行口座凍結前に必要資金を引き出す(銀行)
死亡が金融機関に知られると口座は凍結され、引き出しや振込が一切できなくなります。
葬儀費用や当面の生活費は事前に引き出しておきましょう。
その口座が普段使っている生活用口座の場合、手続きが完了するまで本当に困りますよ!
- 必要書類:キャッシュカードまたは通帳、暗証番号
- 注意点:死亡後に引き出すとトラブルになるため、必ず死亡届を出す前に対応
2. 死亡診断書をもらう(病院)
火葬許可申請や相続手続きの基礎になる書類です。
必ず複数枚(5〜10枚)コピーしておきましょう。
原本を役所に提出してしまうと、また発行してもらわないといけなくなります。
- 発行場所:病院
- 費用:1通3,000〜10,000円程度(病院によって変動)

3. 死亡届の提出(役所)
期限は亡くなった事実を知った日から7日以内になります。
届書を作成し、亡くなった方の死亡地・本籍地または所在地の自治体に提出しましょう。
4. 火葬許可証の取得(役所)
火葬には必ず必要な許可証。死亡届と同時に申請します。こちらも7日以内。
火葬当日に、忘れずに火葬場に持参してください。(葬儀社によっては書類作成を代行して行う場合もあります)
- 必要書類:死亡届 届出人の印鑑(認印でいい場合が多い)と身分証
5. 印鑑証明書をもらう(役所もしくはコンビニ)
相続や名義変更で必要。故人と相続人それぞれの印鑑証明を用意します。
市区町村がコンビニ交付サービス対応なら、コンビニでも発行可能ですし、発行にかかる金額が抑えられます。
急いでいる時に24時間あいているのも助かりますね。そうなるとマイナンバーカード作ってて助かったとも思います。
- 必要書類:印鑑登録カードかマイナンバーカード
- 発行場所:住民票のある市区町村の役所もしくはコンビニ
- 費用:200〜300円

6. 住民票の停止(役所)
死亡届の提出により住民票が削除されます。
その削除された住民票を『住民票の除票』といいます。
この除票の写しを相続や各種解約で使う場合がありますので2〜3枚取っておくと良いです。
7. 公的保険資格喪失届(役所もしくは勤務先)
◎国民健康保険(自営業・フリーランスなど)や後期高齢者医療制度の場合
亡くなった日から14日以内に資格喪失手続きが必要です。
その際に、健康保険証も返却します。
◎社会保険(会社員)の場合
勤務先を通じて亡くなった日から5日以内に健康保険・厚生年金保険資格喪失届を提出する必要があるため、速やかに会社に連絡してください。

例えば、会社員のご主人の扶養に入ってる場合、ご主人が亡くなったら奥さんの保険証はどうなるの?保険証は返すんだよね?
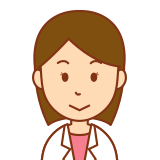
そうね、その時から社会保険の保険証は使えなくなるわ。会社員である別の家族の扶養に入るか、国民健康保険に切り替える必要が出てくるの。
それが国保だと14日以内に手続きしないといけないから時間が短い分、注意が必要なのよ。
8. クレジットカードの解約(カード会社)
使わないカードは早めに解約。余分な年会費の請求を防げます。
カードは、作るときより解約するときのほうが何倍も労力を使います。
自分名義以外なら余計にです。
ですので、普段から不要なカード類は持たないほうがオススメではあります。
9. 運転免許証の返納(警察署)
故人の運転免許証を返納します。本人確認のため死亡診断書や戸籍が必要な場合があります。
10. 保険金の請求(保険会社)
生命保険・医療保険などの請求は早めに。保険証券を確認し、担当者に連絡します。

通常、請求期限は3年と言われてるんだ。
過ぎちゃうと時効になって権利が消滅してしまうから早めに請求するほうがいいね。
必要書類は保険会社によって異なるので、契約先の保険会社に確認してみてください。
11. 光熱費の解約・停止(各社)
電気・ガス・水道・スマホ・インターネットなどを停止または契約者変更します。
独居の場合は解約手続きが、同居している親族がいる場合は名義変更の手続きをしましょう。
不要なものから順次手続きを進めていきましょう。

期限が決まっている手続き
12. 世帯主変更届(役所・14日以内)
住民票上の世帯主を変更します。
13. 所得税納付(税務署・4か月以内)
故人の確定申告(準確定申告)を行います。
14. 未支給年金の請求(年金事務所・5年以内)
受給権者死亡届(報告書)の提出が必要になります。
受給途中で亡くなった場合、請求すれば未支給分を受け取れます。
忘れずに手続きしましょう。
15. 葬祭費請求(自治体・2年以内)
国民健康保険加入者が亡くなった場合、葬祭費(3〜7万円程度)が支給されます。
手続きは喪主本人が行います。

まとめ
家族が亡くなったときは、悲しみの中でも期限がある手続きを一つずつ進めていく必要があります。
このリストをもとに、早めに動くべきものから着手し、必要書類をあらかじめ揃えておくとスムーズです。
この記事は2025年8月時点の情報です。実際の手続きは必ず各機関で最新情報を確認してください。




コメント